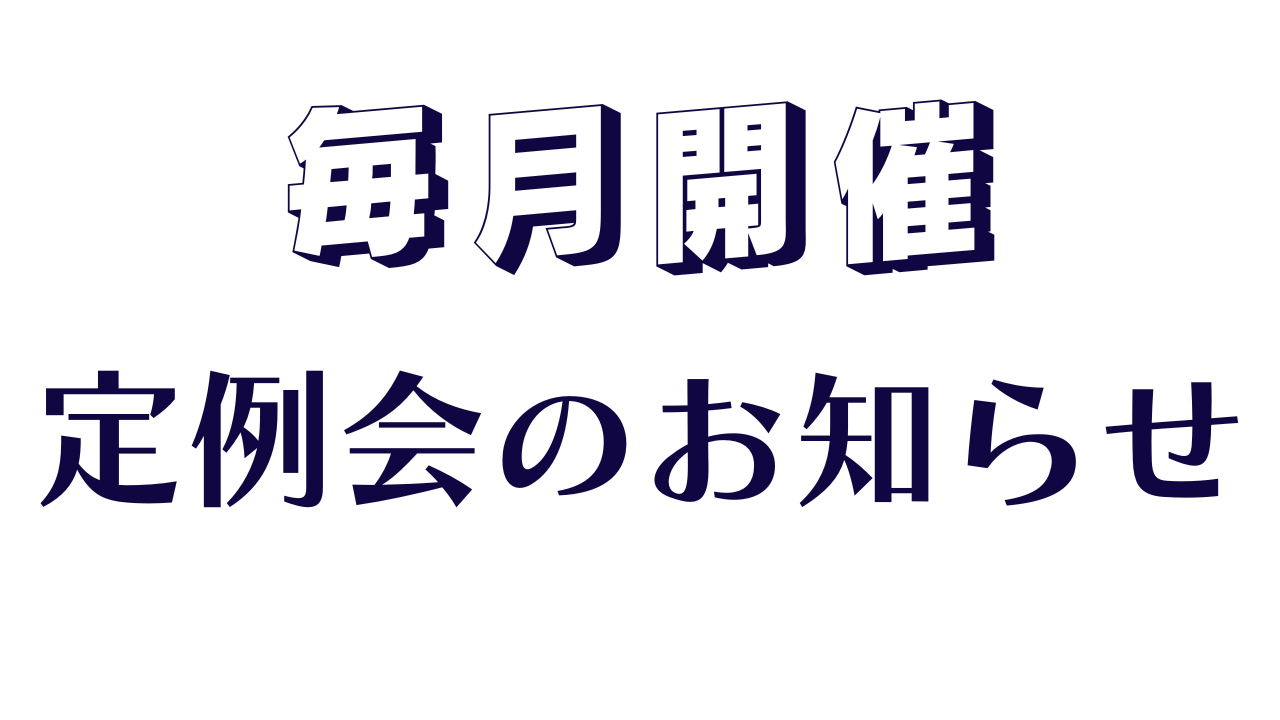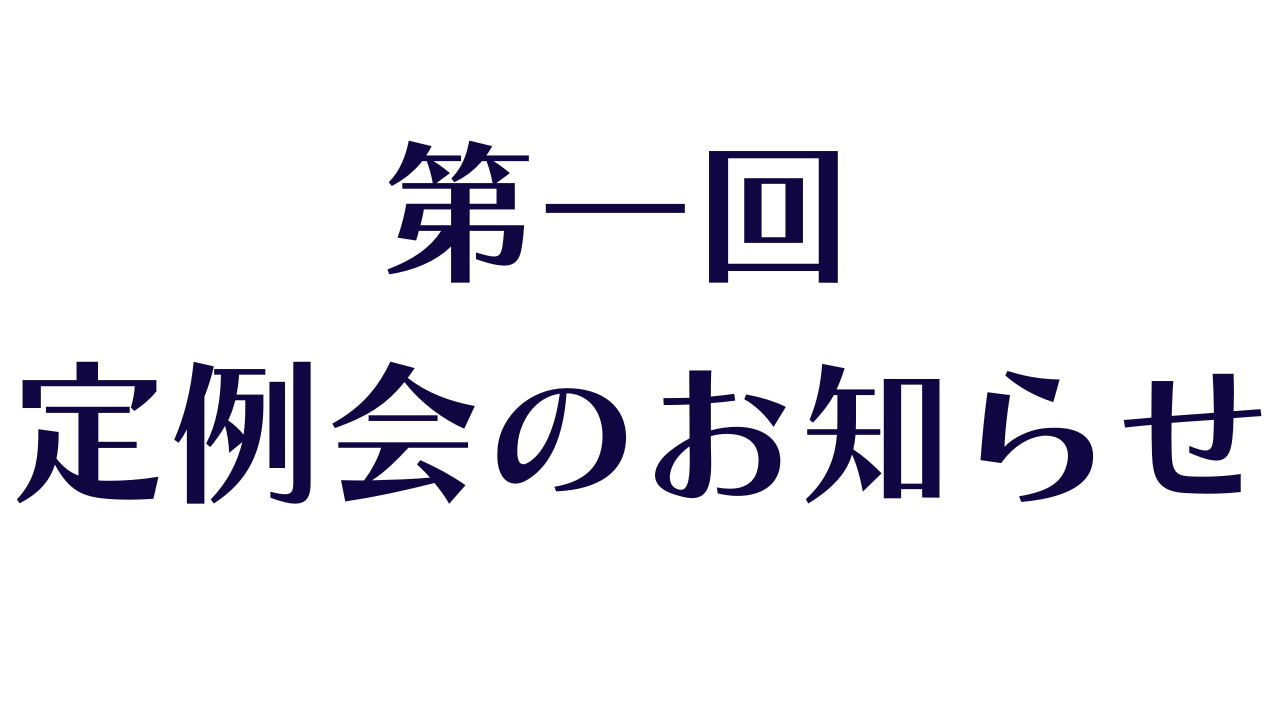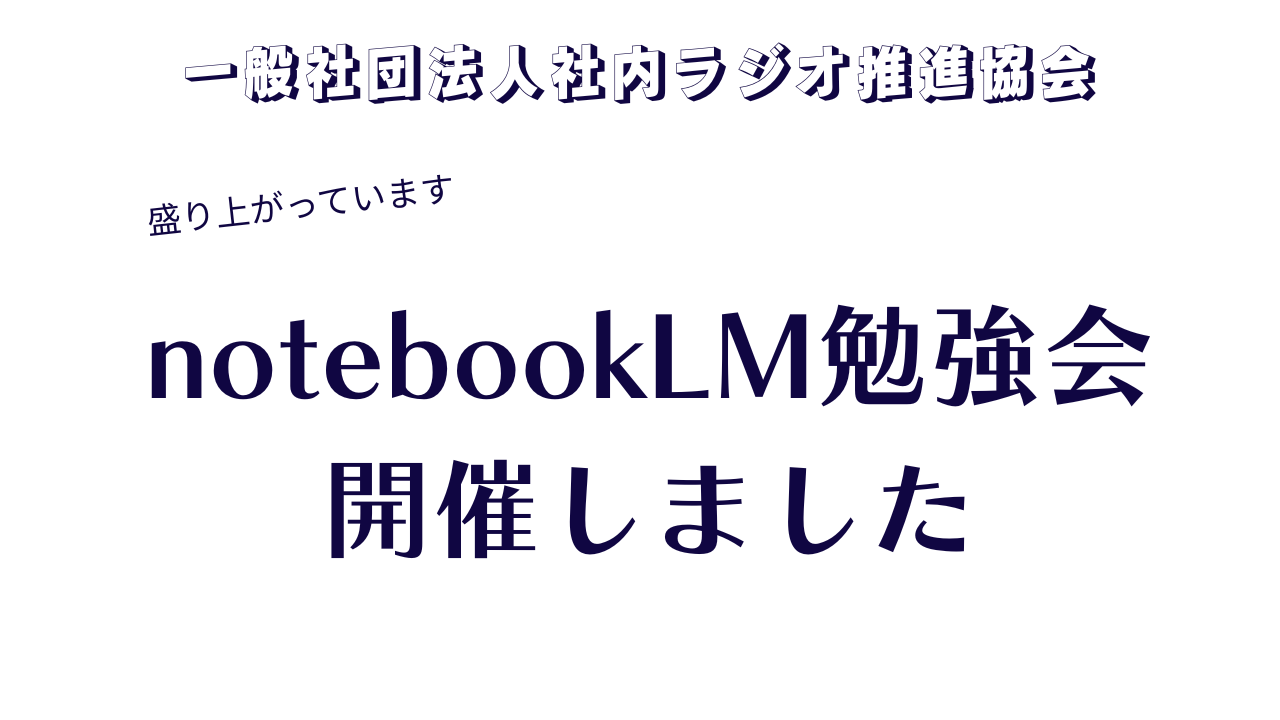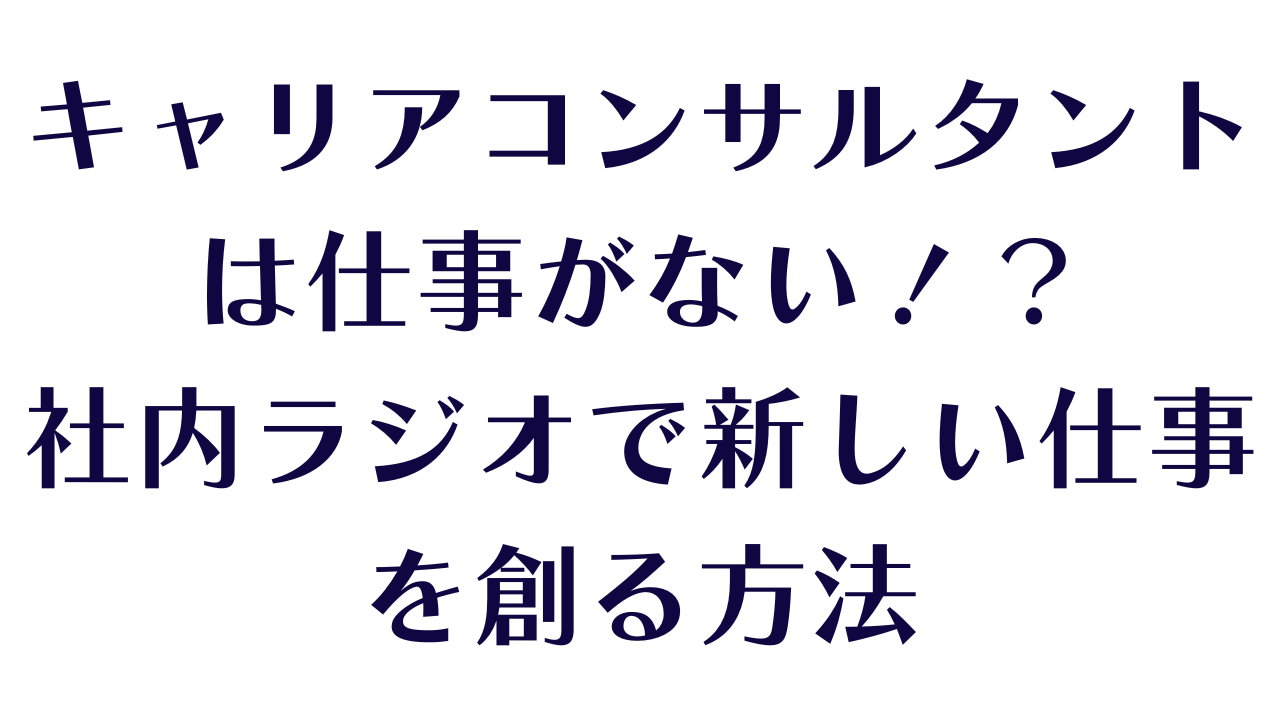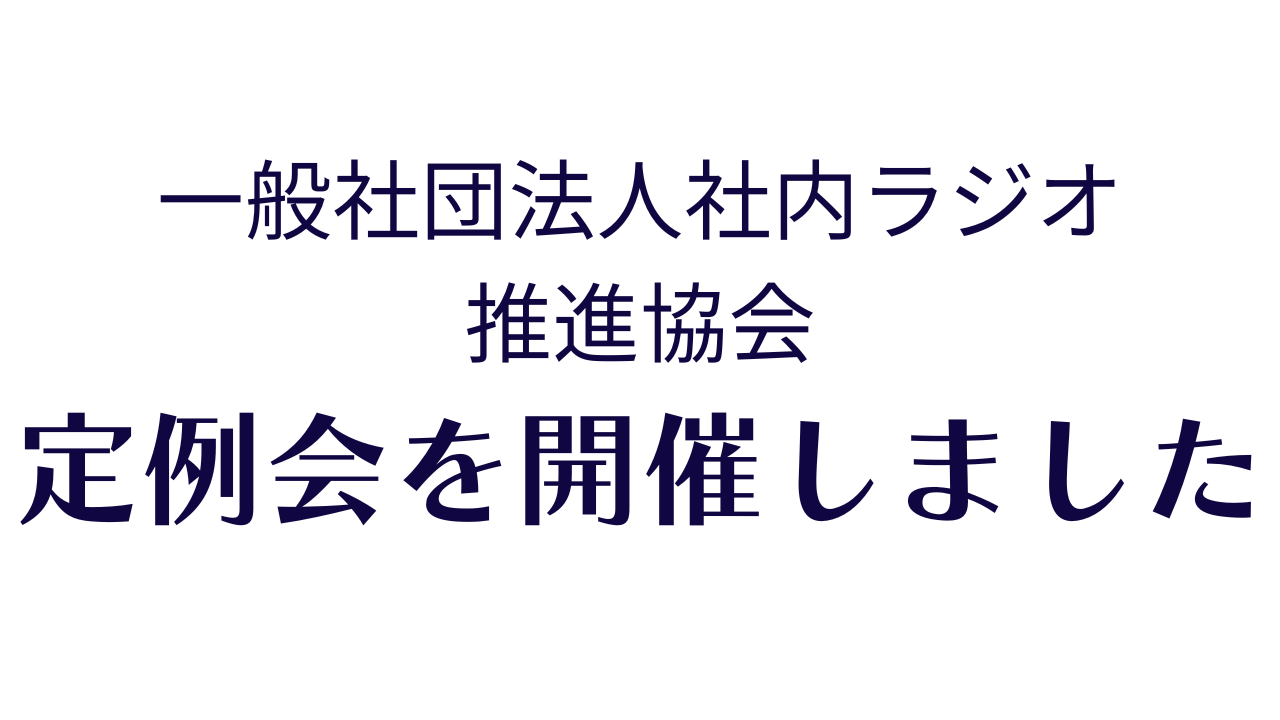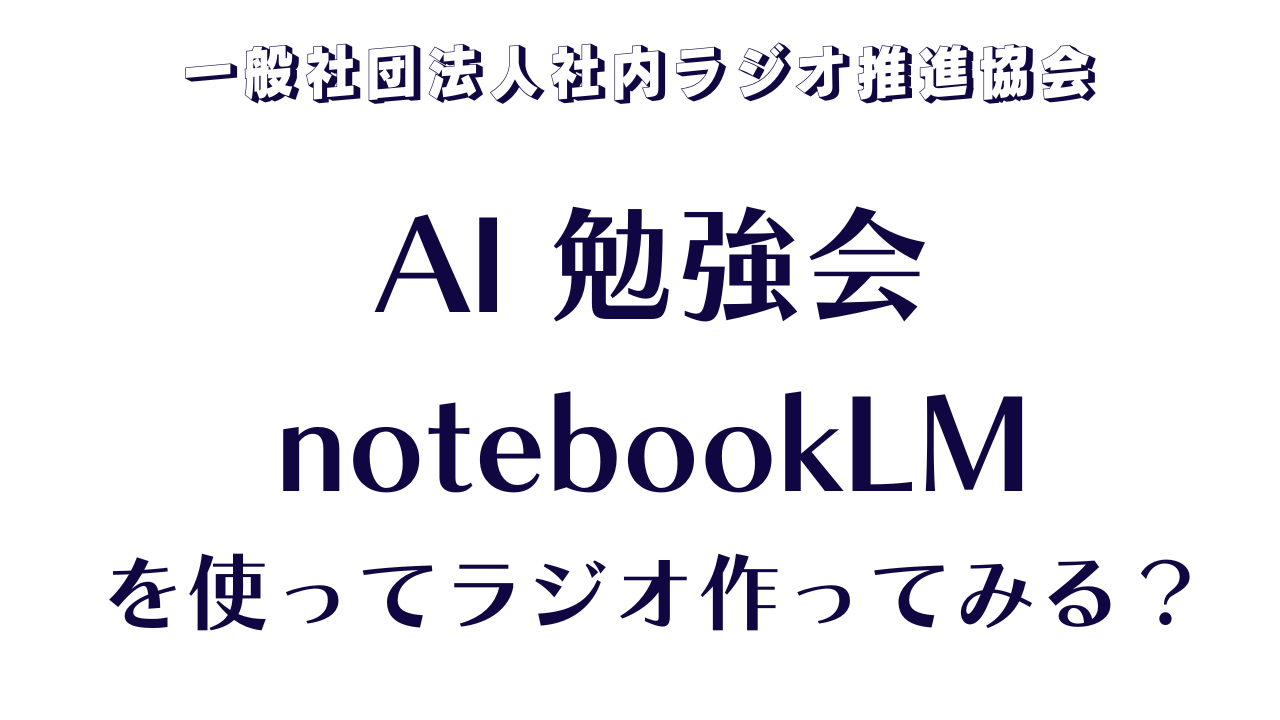ケアの側面からみた社内ラジオ:刑務所の矯正教育放送が示すヒント
社内ラジオを導入したいと考えたとき、「ラジオの価値は?効果は?」と上司に質問攻めにあうことを想定します。ラジオは媒体。ラジオを導入したから「こうなります」と約束するものではありません。
答えは「いえ、ラジオは会社という社会のメンバーの心の拠り所となる『ひろば』みたいなものです。地域に公民館がないと集まれませんよね?」という説明でしょうか。
この記事では、刑務所でのラジオを紹介します。刑務所内で配信されるラジオは見事にこの「ひろば」の役割を果たしている例です。「さいはて社 金山智子編 ケアするラジオ」を参照にしました。
かつて矯正教育放送という取り組みがあった
1960年代、矯正局が、刑務所内で流すために「矯正教育放送」を行っていたといいます。全国一律に放送する「模範的な受刑者たれ」という教育的な内容だったのでしょう。
これが市民権を得るとは思えない。メディアをプロパガンダの道具として使用した戦時中の状況とあまり変わらない。受刑者達がそれをどのように受け止めたのかわからないが、これとは別に、自主放送も各地の更生施設で行われていました。
こちらは、本気で受刑者の更生や心のケアを目的としたものだと思われます。番組は職員が制作していて、福岡の魚市場で働く者のインタビューや出所者の体験談など含まれ、多くの受刑者が関心を持って聞いていた。
しかし、いつしか、この自主放送も形式的になり、マンネリ化も招いた。「本当に更生に役立っているのか」という懐疑的な見方も強くなり、外部のDJを起用して受刑者に寄り添うスタイルに変化していった。
外部のDJが発信することで、音楽を紹介するだけの娯楽的要素の強い番組や、お便り紹介するスタイルの番組なども作られていきました。
自社内でラジオを配信する企業がまだまだ少ない中で、刑務所が実に早くからラジオの有効性に気づき、取り組んでいたという事実は驚嘆に値します。
他者の存在が怖い、自己を開示しにくい状況の中で
刑務所では、他者の存在が怖く、自分の心を表に出すことを困難に感じる受刑者が多いと言われます。
そこでラジオは匿名性を活かし、自己開示を促すきっかけになる。匿名で番組にメッセージを投稿することで、自己と向き合うきっかけになり、他者とのつながりを感じる第一歩になっている受刑者も多いといいます。
同じように、職場でも社員が意見を伝えたり、自分の考えを開示することに抵抗を感じる場合は多いでしょう。社内ラジオでは、匿名での投稿を取り入れることで、社員が自然に自己を表現する場として機能させることもできます。
物語を聞くことで生まれる共感
ラジオの魅力のひとつは、他者の物語に耳を傾ける場となること。ラジオを通して他社の物語を追体験する。共感が生まれたら、自分自身の生き方に重ね合わせたり、選択を見つめ直す機会となり得ます。
たとえば、刑務所内のラジオでは出所者の体験談に多くの受刑者が耳を傾けます。「自分もやり直せるかもしれない」という希望を感じさせる内容が、更生に向けた動機づけにつながるものと考えられます。
社内ラジオで、社員の物語を自分の言葉で語ってもらうことは、実は貴重な経験となり得ます。聞いてる社員はラジオという『ひろば』に集まり、自分と重ね合わせて、心に響いた部分を選び取っていくことを無意識にやっているということです。
ラジオが促す自己理解
刑務所内のラジオ番組では、受刑者が番組にメッセージを出すことで自己と向き合い、自己理解が深まる効果があるそう。これは無視できないくらい心の成長に役立っているといえるでしょう。
自分の話をして、聞いてくれる人がいるという状況において、人は考え、感情を整理します。一度ラジオで他者に対して語ったことは他者の中での真実になりますから、「ラジオで語った自分にならないと」という緩やかな強制力を発揮することにもなるでしょう。
社内ラジオでも、社員が匿名でメッセージを送る仕組みが軌道に乗ると、結構、お便りは集まります。
うまく運用できれば、社員が普段口に出すことのない意見や感情を言葉として表現する場になり、自己理解を促し、職場での行動や考え方にポジティブな変化をおこしていくパワー担っていきます。
ラジオで必要なのは「寄り添う姿勢」
刑務所のラジオでは、外部のDJがフレンドリーであること、寄り添う姿勢で受刑者に対して肯定的であろうとしている。その姿勢は、受刑者にとって自己の確立につながっているといいます。
社内ラジオのDJも同じです。上手に話すことよりも、社員一人ひとりに寄り添い、肯定し、丁寧に届ける姿勢がリスナーの心にすっとはいっていくきっかけになります。
まとめ:社内ラジオは「心のインフラ」
ラジオは、他者とのつながりや自己理解を促す素晴らしいメディアです。刑務所のラジオから学べるのは、相手の心に寄り添い、匿名性を担保し、共感を大切にすること。社内ラジオでもこれらの事例から学び、職場の活性化や社員の成長につなげて行きたいものです。